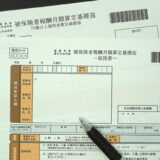事業が成長し、ついに従業員さんを雇用!とても喜ばしいことですよね。
皆様は、従業員の方から育児休業を取得したいと言われたら、どのような手続きが必要かご存知でしょうか?
日本はご存知の通り少子高齢化社会です。少子化対策として、育児休業期間の延長や有期契約従業員の育児休業の取得要件の緩和、マタハラ・パタハラなどの防止措置義務などこれまで様々な法整備を繰り行っており、出産や育児がしやすい労働環境の整備は加速しています。
また、男性に至っては、諸外国に比較して日本は育児に関与する時間が少ないことも問題視されており、国は2025年までに男性の育児休業取得率を30%にしようと様々な少子化対策を行っています。また、2023年4月より、従業員1000人を超える企業は、男性の育児休業取得率を公表しなければならなくなりました。今後はもっと従業員数が少ない企業も対象になると思われます。
また、国や都道府県、市区町村でも様々な育児休業に関する助成金なども整備され、その取得促進の後押しをしています。
育休取得がどんな規模の会社にも広がってきており、中小企業には関係ないとは言えない社会になっている今、事業主は何をしなければならないのか、社労士が解説いたします。
目次 非表示
- 育児休業とは?
- 出生時育児休業(通称:産後パパ育休)とは?
- いつからお休みが取れるのか?
- 育児休業は、申し出た従業員に必ず取らせないといけないのか?
- 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
- 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
- 事業主が行う育児休業から復帰後の手続きの概要
- 「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)」
- 「育児休業給付受給資格確認票・育児休業(出生時育児休業)給付金支給申請書」
- 「休業開始時賃金月額証明書」をハローワークへ提出する。
- 「育児休業等終了時報酬月額変更届」
- 「養育期間標準報酬月額特例申出書」
- 出生時育児休業・育児休業中の従業員の賃金や保険料負担の扱いについて
- 休ませている間の社会保険料は手続きをすれば事業主も従業員も納付免除される
- 休業中の雇用保険料について
- 休業中に従業員が受けることができる給付金は二種類ある
- 出生時育児休業給付金
- 育児休業給付金
- パパママ育休プラス制度を利用する場合
- 育休中に働くことはできるのか?
- 事業主が事前に整備しておきたいこと
- さいごに
- 社会保険の手続きを顧問料なしのスポット(単発)で行うなら
会社員として働く方々が育児に専念するために、子どもが※1歳になるまでの間で分割して2回休暇を取ることができる制度です。育児休業は、1歳未満の子どもを養育する労働者から申し出があった場合、取得させなければならない義務があります。
※1歳になる時点で保育所に入れない等、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限り1歳6か月まで(再延長2歳まで)育児休業ができます。
産休(産前・産後休業)との違いは?
産休とは、出産するための準備期間と、出産後に身体を回復させる期間に休業できる制度です。産休は女性のみが取得できることが育児休業との大きな違いになります。
産休期間は、出産予定日の6週間前から出産後8週間までです。産前に関しては従業員が休業を申請した場合、労働させてはならないとしていますが、産後は本人からの申請に関係なく、休業させることが法律で義務付けられています。
ただし、産後6週間を過ぎて医師から許可が出た場合に限り、8週間を待たずに復職が可能です。
男性の育児休業取得を促進するために新設される制度で、従来の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間(28日間)までの間の労働者が希望する期間、2回まで分割して取得することができます。「子供の出生から8週間以内」という期間が、女性労働者の産後休業と時期が重なることから、「男性版産休」などと呼ばれることもあります。
| 対象者 | 男性労働者 (養子の場合等は女性も取得可能)有期契約労働者は、申出時点で、出生後8週間を経過する日の翌日から起算して6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、対象となります。 |
| 労使協定の締結により対象から除外できる者 | ①入社1年未満の労働者 ②申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
| 期間 | 子の出生後8週間以内に4週間(28日間)までの間の労働者が希望する期間 |
| 申出期限 | 原則休業の2週間前までに申出 ※雇用環境の整備等について、法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、申出期限を1か月前までとすることができます。 |
| 分割取得 | 2回まで分割して取得可能(まとめて申出ることが必要) |
| 休業中の就業 | 労使協定の締結により、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |
出生時育児休業と現行の育児休業との違い
出生時育児休業と通常の育児休業は異なる制度のため、併用可能です。出生後8週間以内の育休の申し出を一律「出生時育児休業」の申し出として扱うことは認められず、どちらの申し出なのか不明な場合は、従業員にどの制度を利用するのか確認が必要です
出生時から連続で育休が取れない男性には、出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業とを活用することで最大4回に分けて休業することができるので、育休が取りやすくなります。最初からまとまった長期間で育休が取れる場合は、通常の育児休業を利用されるのが良いと思います。
| 出生時育児休業 | 現行:育休制度 | 旧:育休制度 | |
| 対象期間 | 子の出生後8週間以内 | 原則、子が1歳(最長2歳)まで | |
| 取得日数 | 最大4週間 | 期間内で申し出た日数 | |
| 申請期限 | 休業日の2週間前 | 休業日の1か月前 | |
| 休業中の就業 | 労使協定の締結により、労働者の合意した範囲内で可能 | 不可 | |
| 分割取得 | 2回まで分割可能 | 2回まで分割可能 | 不可 |
| 1歳以降の延長 | ー | 開始日を柔軟に選択可能 | 開始日は1歳又は1歳半の開始日 |
| 1歳以降の再取得 | ー | 特別な事情に限り再取得可能 | 不可 |
分割して取得する際の申出
出生時育児休業を2回に分割して取得する場合は、1回目の申出時に、出生後8週間のうちいつ休業しいつ就業するかについて、初回の出生時育児休業の申出の際にまとめて申出ることが必要です。法律上、まとめて申出ない場合には、事業主は2回目の申出を拒むことができるものとされています。
お休みを取得する方が出産をした女性であれば、産後休業終了翌日から、本人の申し出た期間を取得することができます。
また、男性は子が出生していない場合は、出産予定日から取得することができます。
※育児関係の「子」の範囲は、労働者と法律上の親子関係がある子(養子を含む)のほか、特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子や養子縁組里親に委託されている子等を含みます。この場合、原則としてその1歳歳(保育所等に入所できない等の理由がある場合は1歳6か月、それでも保育所等に入所できない等の理由がある場合は2歳。)に満たない子を養育するためにする休業を申し出ることで育児休業を取得することができます。
育児介護休業法第5条により、対象となる方は休ませなければなりませんし、そもそも事業主は育休を取得しやすい環境を作るため、以下のような義務もあります。
育児休業の取得促進のための事業主の義務は「環境の整備」「周知・意向確認」
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるよう、事業主は以下のいずれかの措 置を講じなければなりません。※複数措置が望ましいです。
- 育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施
- 育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業休取得事例の収集・提供
- 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
上記申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。 ※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
- 育児休業・出生時育児休業に関する制度
- 育児休業・出生時育児休業の申し出先
- 育児休業給付に関すること
- 労働者が育児休業・出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
育児休業・出生時育児休業が取得できる対象者は誰か?
育児休業法では、育児休業をすることができるのは、原則として1歳(最長2歳)に満たない子を養育する男女労働者とされています。
※日々雇い入れられる者は対象から除かれます。
正社員だからお休みができる、パートだからできない、という雇用区分で権利が発生するというものではありません。取得できる方の要件については以下となります。
有期雇用契約の従業員も休ませなければならないのか?
期間を定めて雇用される者は、子が1歳6か月になる日の前日(※)までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない場合は、育児休業を取得できます。
出生時育児休業は子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して、8週間を経過する日の翌日から6か月
上記に該当している人でも、申し出を拒むことが出来る場合がある
労使協定の締結をすることで、以下の方からの申し出を拒めるようになります。
- 入社1年未満の従業員
- 申出の日から1年(※出生時育児休業については8週間)以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
労使協定を締結していないのに申し出を拒むことはできません。運用する場合は必ず労使協定を締結してください。
所轄の年金事務所へ届出をすることで事業主も従業員も該当期間は社会保険料が免除となります。
所轄のハローワークへ提出をすることで、従業員は給付金を受け取れます。
育児給付金の給付額の基準を決める書類で、事業主が作成するものです。育児休業給付金支給申請書と一緒に所轄のハローワークに提出します。
仕事復帰した月から3か月後に所轄の年金事務所へ提出します。仕事復帰した時の標準報酬月額は、産休に入る前の標準報酬月額になります。仕事復帰した際に育児があるため短時間勤務で働くことになる場合、その分賃金が下がることがあります。そうなると、賃金は下がっているのに社会保険料は高いままになってしまいますので、仕事を復帰してから3ヵ月後に社会保険料を下げる手続きを行います。
「育児休業等終了時報酬月額変更届」と同時に所轄の年金事務所へ提出します。育休明けで標準報酬月額が下がった人の年金が下がらないようにする手続きです。厚生年金は納付した保険料によりもらえる年金額が変わります。育休明けの時短勤務により納付する社会保険料が下がっても、将来もらえる年金額が下がらないよう育休前の社会保険料を払ったとみなして年金を計算するという特例の制度になります。
休業期間は無給でも問題はありません。(基本はノーワークノーペイの考えで問題ありません。)中には有給とする企業もありますが、休業中の給料までを補償する必要はなく、会社がどう運用していきたいかを考えて会社ごとに決めることができます。
休業中の賃金については、あらかじめ社内規程に明記しておくことで、従業員に無駄な誤解をさせずに済むので、就業規則や育児休業規程を作成しましょう。
手続きの流れ
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)を所轄の年金事務所へ提出することで事業主も従業員も社会保険料が免除となります。免除されている期間は「納付したもの」とみなされるので、老後に受け取る年金額に反映されます。
この申出は、育児休業等の期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に行わなければなりません。
実際の社会保険料負担が免除される期間
この申出により、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間の、毎月の報酬にかかる保険料が免除されます。
また、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等に限る)。
賞与・期末手当等にかかる社会保険料
育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料についても免除されます。ただし、令和4年10月1日以降に開始する育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。
雇用保険料は賃金の支払いがあった場合に発生するものなので、休業中に賃金の支払いがなければ、事業主も従業員も負担することはありません。
出生時育児休業をした場合は出生時育児休業給付金、育児休業をした場合は育児休業給付金が、雇用保険から支給されます。
対象者
- 雇用保険の被保険者であること
- 出生時育児休業前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12ヵ月以上あること
- 出生時育児休業期間中の就業日数が、最大10日(※)(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること(※)28日間の出生時育児休業を取得した場合の日数・時間です。 28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
- 出産予定日から8週間以内に4週間の出生時育児休業を取得していること(2回まで分割取得可)
- 期間を定めて雇用される方の場合、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
手続きの方法
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をハローワークへ提出する必要があります。
いくらもらえるのか
支給額=休業開始時賃金日額x出生時育児休業期間の日数(28日が上限)x67%
※事業主から賃金の支払いがある場合は調整されることがあります。
※支給された日数は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通算されます。
対象者
- 雇用保険の被保険者であること
- 育児休業前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)11日以上または就業した時間数が80時間以上ある完全月が12ヵ月以上あること
- 1歳未満(パパママ育休プラス制度利用は1歳2か月、更に保育所等の問題で延長する場合は最大2歳)の子を養育するために、育児休業を取得していること(令和4年10月より2回まで分割取得可)
- 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること
- 育児休業中の1ヵ月ごとに、育児休業開始以前の給料の80%以上が支払われていないこと
- 期間を定めて雇用される方の場合、養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
手続きの方法
「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をハローワークへ提出する必要があります。
受給資格確認手続きのみ最初に行う場合は初回の支給を行う日まで、初回支給申請も同時に行う場合は育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までに行って下さい。
申請は原則として2か月に一度ですが、被保険者本人が希望する場合、1か月に一度行うことも可能です。
いくらもらえるのか
支給額=休業開始時賃金日額x休業期間の日数x67%(180日まで)
支給額=休業開始時賃金日額x休業期間の日数x50%(180日を超えたら)
※事業主から賃金の支払いがある場合は調整されることがあります。
※すでに支給されている出生時育児休業給付金がある場合は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通算されます。
父母共に育児休業を取得する場合は、以下すべて満たすと、子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、最大1年まで育児休業給付金が支給されます。
- 育児休業開始日が、当該子の1歳に達する日の翌日以前であること
- 育児休業開始日が、当該子に関わる配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること
- 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
手続き
原則、子が一歳に達する日を含む支給対象期間までの支給申請時に、以下添付書類を提出する必要があります。
・世帯全員について記載された住民票の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの
・配偶者の育児休業取り扱い通知書等、支給対象者の育児休業開始日が当該子の一切に達する日の翌日以前で、かつ当該被保険者の配偶者の育児休業の初日以後であることを確認できるもの
育児休業中は原則就業することは不可となっていますが、出生時育児休業については、労使協定を締結している場合に限り、就業することが可能です。なお、就業可能日等には休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分など上限があります。
就業時間や日数によっては、出生時育児休業給付金が調整支給されますので、注意が必要です。
休業の種類が2つあり、また、休業の要件と給付金の要件など、複雑に感じることの多い制度です。事業主の皆様にはあらかじめ、
- 育児休業の対象となる労働者の範囲等につい
- 取得に必要な手続(申し出や変更のルールなど)
- 休業期間について
- 休業期間の賃金の支払の有無
などの項目について、就業規則や育児休業規程に記載をしておくことで、都度運用について考える必要が無くなり、また従業員への周知漏れから生じる取得権利にまつわるトラブル発生のリスクもなくなります。
今後も育児休業取得を促進する法改正等、法整備はどんどん進んでいく流れがあります。
厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査結果」によれば、88%が男性の育休取得に「賛成」と回答しており、うち就活層では97.8%とほぼ100%が賛成をしています。一方で経営層の賛成は76%にとどまっているということでした。若い世代にとっては「当たり前」になりつつある育休について、性別関係なく「育休が取得しやすい会社」が今後選ばれていくことは想像に難くありません。
育休は権利だから取らせないといけないというお考えだけではなく、若手を採用したいとお考えの事業主の皆様におかれましては、育休取得について、公表の義務化が進んでおり、採用や人材定着に直結する重要指標であるということをご理解頂ければと思います。
一方で育休は度重なる法改正、いつから該当するのか等の個別ケースなども多いため、これまで様々な手続きをご自身で対応されていた事業主の方でも、専門家へ依頼するきっかけとなるタイミングは従業員の育児休業取得時だと言われています。
スポット手続きとしての給付金申請や社保免除の手続きや、従業員への周知のための育児休業規程の作成なども、顧問契約なしでスポットでの対応が可能です。もちろんご希望があれば顧問契約も対応しております。ぜひご検討ください。
・社労士Cloudなら「全ての手続き」を顧問料なしのスポット(単発)で簡単かつ迅速にお手続きできます。こちらからお問い合わせください。

社労士Cloud
社労士Cloud
https://sharoushi-cloud.com/全国のあらゆる社会保険手続きをスポット(単発)で代行するWebサービス【社労士Cloud】の運営者| 超絶早い・メチャ安い・懇切丁寧が売りです| 750社以上の企業様や全国津々浦々の税理士先生にご利用頂いております| Web・電話・公式Line・Chatwork・対面で手続き即日完結|顧問契約も可能